ペンチャン待ちとはシュンツを作るための待ちの一つです。
あなたはペンチャン待ちは嫌いですか?
一番上がれそうにない待ちだと考えていますか?
みなさんの評判はあまりよくないペンチャン待ちですが、いつも両面待ちにはならないのが麻雀の面白いところ。
今回はそんなペンチャン待ちの切り時、扱い方など動画も交えて読みやすい記事にしました!
というわけでこんにちは!

NPO法人 健康麻雀グループの河原 健治です。
私はこれまで16年間、柏市内で初級者のお客様に対して麻雀を教えてきました。
みなさんがよく間違える疑問や、強くなるために必要な知識はすべてわかっています。
よくあるペンチャン待ちの扱い方にもテクニックがあるんです。
うまく扱うことで上がりやすくもなります。
まず最低限必要な知識を頭に入れ、そして少しステップアップした技術を身に付けることで麻雀が上手くなるはず。
「なかなか麻雀が上手くならない!」
と考えているんでしたら、今回はぜひそのチャンスだと思って読み進めて下さい!
ペンチャン待ちから学ぶ知識の多いことに気が付くはずです。
麻雀をする以上ペンチャン待ちは避けて通れません。
みんなが嫌いなペンチャン待ちの扱いがわかれば強くなると思いませんか?
なお中級者の方のために最低限必要な知識は最後に解説し、みんなが知りたいポイントから書きました。
基礎知識が不安な方は最後から読むこともオススメします。
それでは参りましょう!
↓当店の公式サイトもご覧ください↓
はじめてのご参加の方全員に¥3000分の割引券をプレゼント!
1. みんなが悩むペンチャン落としのコツ
1-1.ペンチャンとカンチャンの比較
麻雀をしていると必ずこんな形に遭遇します。
上図は序盤の牌姿とします。
ここに ![]() を引きました。
を引きました。
さて何を捨てたら良いでしょうか?
このケースでは![]() と
と![]() を 順に捨ててペンチャンを嫌うのがセオリーです。
を 順に捨ててペンチャンを嫌うのがセオリーです。
これは典型的なペンチャン落としの 例です。
このようにペンチャンよりカンチャンの方が優先されるのは、両面へのなりやすさが違うからです。
カンチャンの方が両面に変わりやすいから大事にされるのです。
この点に関しては後ほど詳しく解説します。
麻雀では基本!ペンチャンよりカンチャンの方を大事に残す!
![]() と
と![]() ではどっちから捨てるのか?
ではどっちから捨てるのか?
それにはケースにより違うことを知っていますか?
1-2.ペンチャン落としは内側からか外側からか?

ペンチャンを落とすといっても、 内側から落とすのか?外側から落とすのか?
![]()
![]() の場合に内側の
の場合に内側の![]() からか?外側の
からか?外側の![]() からか?ということです。
からか?ということです。
こんな疑問を持ったことはありますよね!
麻雀は一手切り遅れることで、それが当たり牌になるケースが多くあります!
一手切り間違えることでせっかくのメンツを逃すこともあります。

小さなことのようですが以外にもこれが重要なんですよ!
これについて解説します。
1-2-1.基本的な考え方
麻雀の基本的な考え方です。
序盤では4つメンツ素材を集めていきます。
これは 早いテンパイに向けて、四人が同じように行っています。
麻雀の牌にはA から Dの4つランクがあります。
この点に関しては後述していますから確認してください。
簡単に言えば真ん中牌(牌ランクAやB)の方がメンツになりやすいのです。
数牌なら、2から8が中心。
そして両面ターツがみんな大好きです。
素材が集まれば中盤からは不必要な部分をカットしていきます。
通常は中盤~終盤ではテンパイしている方がいます。
またリーチもかかるかもしれません。
ですから不必要なペンチャン部分をカットする場合は、危険な内側から捨てるのがセオリーになります。
![]()
![]() なら
なら![]() からです。
からです。
基本的に真ん中牌の方がメンツになりやすいと書きました。
メンツになりやすい牌=※中張牌(チュウチャンパイ)=危険牌ということです。
※中張牌(チュウチャンパイ)
数牌の2~8の牌のこと
ペンチャン落としの基本は内側から!
内側の中張牌の方がメンツになりやすい牌(危険牌)だからです。

初心者のうちはこれだけでもOKだよ!
1-2-2.外側から落とす場合!
ここからは自分のレベルが徐々に上がってきたら知識として身に付けていこう!
ペンチャンを落とす場合は、すぐに![]() を引いた場合のことを考えます。
を引いた場合のことを考えます。
![]() を落としてすぐに
を落としてすぐに![]() を引いた場合、
を引いた場合、![]()
![]() の両面の形になります。
の両面の形になります。
これはもちろん※フリテンになりますが、残しておいても良い場合もあります。
上がり牌が自分の捨て牌にあればフリテンになります。フリテンはロン上がりできません。
それは上図のように、残りのターツがすべて両面の形でない場合です。
の中で両面の形は![]()
![]() のひとつだけです。
のひとつだけです。
こんなケースの場合はフリテンといえども、残しておくのが良いでしょう。
そのためにから![]() (外側)を落とすのです。
(外側)を落とすのです。
もうひとつ例を出します。
上図を見てください。
ここに索子の![]() を引いてきました。
を引いてきました。
あなたなら何を捨てますか?
この手牌は、頭が確定してません。
そしてタンヤオができるかもしれませんね。
こんな時は外側の![]() から捨てて、
から捨てて、![]() の重なりに期待します。
の重なりに期待します。
ペンチャン以外の残りの形でカンチャンが多い場合には外側から落とす!
しかしフリテンになった場合には十分注意すること。
タンヤオ役が出来そうなで、頭が確定していない時は外側から落とす!
1-2-3.内側から落とす場合!
上図を見てください。
ここに![]() を引いてきました。
を引いてきました。
ドラは ![]() とします。
とします。
あなたなら何を捨てますか?
![]() はツモ切りですか?
はツモ切りですか?
ここはドラの![]() を引いた時の事を考え、 ペンチャンを落とすのがセオリーです。
を引いた時の事を考え、 ペンチャンを落とすのがセオリーです。
この場合のペンチャンは内側から落とすのか外側からか?
同様にペンチャン以外のターツを見てください。
両面と 役牌のトイツの良い形が残っていますね。
こんな時は ![]() (内側)から落として、完全にペンチャンと決別するのです。
(内側)から落として、完全にペンチャンと決別するのです。
残りの形が良いために![]() を引いて、フリテンをわざわざ残すことは考えなくても良いのです。
を引いて、フリテンをわざわざ残すことは考えなくても良いのです。
ペンチャン以外の残りの形が両面形で良形の場合には内側から落とす!
1-2-4.内側か外側かは他家の捨て牌から判断する

1-2-1章では内側から落とすのがセオリーだとしました。
これは内側牌=メンツになりやすい=中張牌=※危険牌だからです。
でもいつもそうだとは限りません。
これはあくまでも一般的な話です。
今他家の3人の捨て牌が下図のようだったとします。
A ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
B ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
C ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたがこの場合にペンチャンの![]()
![]() を落としたいと思った場合に考えてみて下さい。
を落としたいと思った場合に考えてみて下さい。
このケースでは明らかに危険なのは![]() の方です。
の方です。
ですから先に落とすのは外側の![]() からになります。
からになります。
この考え方はあくまでも他家がテンパイしていないという前提で考えたことです。
テンパイしていなければ、他家の危険牌から先に落とした方がいいですからね!
このように麻雀では一瞬で状況に合わせた打ち方が求められます。
セオリーとはあくまでもセオリーだということを知って下さい。
「そんなことまで見ていられるかよー」
こんな風に思うかもしれませんが、徐々に慣れて短時間でも見られるようになります。
ペンチャン落としは他家の捨て牌を見て、危険牌から先に落とす。
これは他家がテンパイしていないことが前提の考え方。
1-3.ペンチャンとトイツの比較
ペンチャン落としで悩むのは、なにもカンチャンだけではありません。
下図のようなトイツが多くなるケースでも、よくわからないですよね!
上図のような場合に、![]() を引いてきました。
を引いてきました。
こんな時あなたなら何を捨てますか?
捨て牌候補は下図ですね。

消去法で絞り込むと早く答えが出るかもよ!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() の中のどれかです。
の中のどれかです。
まず考えなくてはいけないのが、![]() を刻子にした時の頭です。
を刻子にした時の頭です。
今のところ、![]()
![]() が有力候補です。
が有力候補です。
ですから![]() の切りは避けたいところです。
の切りは避けたいところです。
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]() は、それぞれ2枚と3枚で構成されています。
は、それぞれ2枚と3枚で構成されています。

麻雀というのは2枚より3枚あった方がメンツが出来やすいと思って下さい。
しかも![]() と
と![]() は真ん中牌(牌ランクA)です。
は真ん中牌(牌ランクA)です。
両面への変化も期待できる形です。
この場合はペンチャン落としで、内側の![]() を落とすことで正解です。
を落とすことで正解です。
では下図です。トイツを少し変えてみました。
この手牌に![]() を引きました。
を引きました。
さてどうしますか?
消去法で考えれば、
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() のどれかになりますね。
のどれかになりますね。
この場合でもペンチャンの![]()
![]() を落とす方がいいようです。
を落とす方がいいようです。
考え方は、![]() の鳴き仕掛けができることから※ポン材を残すことが最善だと思います。
の鳴き仕掛けができることから※ポン材を残すことが最善だと思います。
つまり![]()
![]() と
と![]()
![]() を残し
を残し![]()
![]() を内側から落とします。
を内側から落とします。
※ポン材とは
トイツのこと。ポンができる材料のこと。
の形でテンパイしたとしても、
のような手替わりも考えることができます。
リーチをかけてしまうと手替わりできませんが、
![]() をポンした時などは特にそうだということがわかりますか?
をポンした時などは特にそうだということがわかりますか?
このような例を出すと、ほんとにペンチャンは使えないようなイメージなりますね。
でも実際の状況では、
の手牌で![]() をポンした場合に、
をポンした場合に、![]() や
や![]() がすでに他家によって捨てられている場合があります。
がすでに他家によって捨てられている場合があります。
残りは最大で2枚+2枚=4枚。
このうち何枚捨てられているかで考えるケースがほとんどかもしれません。
もし![]() と
と![]() が一枚ずつ捨てられていて、
が一枚ずつ捨てられていて、![]() が一枚も場に捨てられていないのであれば、
が一枚も場に捨てられていないのであれば、![]() のトイツ落としでもいいでしょう。
のトイツ落としでもいいでしょう。
このように考えると麻雀は状況により、判断がとても難しいゲームということがわかると思います。
鳴き仕掛けができるケースでは、ポン材を残してペンチャンを内側から落とす。
残り枚数には気を付けること!
メンツ素材は2枚より3枚の方がメンツ作りには有利だよ!
2.プロ動画で実践的にペンチャン落としを見てみよう
2-1.マルジャン放送局第48回ー多井隆晴プロのペンチャン落とし
上図の動画の東四局(42分20秒辺り)をご覧ください。
ドラは![]() で多井プロは北家。
で多井プロは北家。
から7巡目に![]() ツモで
ツモで![]()
![]() のペンチャン待ちでテンパイしますが、
のペンチャン待ちでテンパイしますが、![]() を落としていきます。
を落としていきます。
![]() を落とせばテンパイの手牌ですが、ドラも見えていないのでここはテンパイを崩します!
を落とせばテンパイの手牌ですが、ドラも見えていないのでここはテンパイを崩します!
![]() から落としたのは、
から落としたのは、![]() を引いてトイツにしてシャンポン待ちを考えてのことだそうです。
を引いてトイツにしてシャンポン待ちを考えてのことだそうです。

みなさん!もしかして「リーチ!」とか言ってないですよね?
子でしかもドラ無しでこんなリーチは厳禁!
こんな時は、ドラを持っていたり、良い手牌の他家、親などに攻め込まれるパターンです。
落ち着いてペンチャン落としです。
![]() の打牌後にすぐ上家からリーチがかかり、多井プロはオリ打ちとなります。
の打牌後にすぐ上家からリーチがかかり、多井プロはオリ打ちとなります。
つづいて!
南二局(48分10秒辺り)の手牌。
上図の手牌から6巡目にを![]() 引いて、
引いて、![]() を落とします。
を落とします。
これは![]()
![]() の部分がカンチャンで不安なために、
の部分がカンチャンで不安なために、![]() が両面になることを期待してのペンチャン落とし。
が両面になることを期待してのペンチャン落とし。
もしこのピンズの部分が両面であれば![]() を落とし、ペンチャンを残したと予想します。
を落とし、ペンチャンを残したと予想します。
しかし、ピンズの下の部分やマンズの![]()
![]() が完成するにしたがってペンチャンは落とすことになるケースが多いはずです。
が完成するにしたがってペンチャンは落とすことになるケースが多いはずです。
2-2.マルジャン放送局第57回ー多井隆晴プロのペンチャン落とし
上図で東四局(16分39秒辺り)西家の多井プロの手牌。
ドラは![]() 。
。
5巡目に![]() を引き
を引き![]() 落としです。
落としです。
これはダブル筋落としと言って、![]()
![]() と
と![]()
![]() の部分で欲しい牌
の部分で欲しい牌![]() が重なるために、片方のターツを見切る切り方です。
が重なるために、片方のターツを見切る切り方です。
その分![]()
![]() を残し
を残し![]() の受け入れに期待したのです。
の受け入れに期待したのです。
麻雀ではできるだけ欲しい牌が重ならないように、なるべく広い受け方をします。
実践ではとてもよくあるケースですから覚えておいてください。
2-3.マルジャン放送局第25回ー石橋伸洋プロのペンチャンキープ
上図の東四局(1時間20分25秒辺り)親の手牌を見て下さい。
ドラは![]()
この手牌から![]() を引きます。ドラは
を引きます。ドラは![]() ですが、それまでキープしていた
ですが、それまでキープしていた![]() も
も![]() を引いたことで、ここでリリース。
を引いたことで、ここでリリース。
ソーズは三面待ち、![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]() の部分は
の部分は![]() と
と![]() と
と![]() の受け。
の受け。
ここで受けとしてはまずまずとします。
このあと![]() を引き、
を引き、![]()
![]()
![]() の三面待ちでリーチとします。
の三面待ちでリーチとします。

![]()
![]() が
が![]()
![]()
![]() となったところで、2枚から3枚ですね。
となったところで、2枚から3枚ですね。
得にペンチャンやカンチャンをこういった感じで「厚めに残す」ことは大事!
「1.3章ペンチャンとトイツの比較」でも書きましたが重要ですよ!
もし上図の形で![]() 、
、![]() 、
、![]() などの牌を引いた場合に1枚捨てるとすると
などの牌を引いた場合に1枚捨てるとすると![]() になる。
になる。
これは一番来そうなところを優先させる考え方です。
それは両面の![]()
![]() で
で![]()
![]() の部分。
の部分。
![]()
![]()
![]() の形では
の形では![]()
![]() を引き、メンツになるケースが多いはず。
を引き、メンツになるケースが多いはず。

これもかなりのポイントだよ!
メンツ作りは「一番強いところは薄めに、弱いところは厚めに構えるのが基本」
この場合の強いところは![]()
![]()
![]() 、
、
弱いところは![]()
![]()
![]() や
や![]()
![]()
![]() や
や![]()
![]()
![]() のことですよ!
のことですよ!
わかるかな?
![]()
![]()
![]() は
は![]() や
や![]() が来ればメンツになる、弱いところに多くの可能性を持たせる残し方をします。
が来ればメンツになる、弱いところに多くの可能性を持たせる残し方をします。
3.上がりやすいペンチャン待ちを作れ

ペンチャン待ちには4枚しか上がり牌がなく、両面待ちと違ってその重要度は低いとされる。
そのペンチャン待ちでも意外に上がりやすい時があります。
ホントにそんな時があるの?
麻雀をしているとよく登場する、「迷彩や引っかけ」というものです。
それでは見て行きましょう!
3-1.チャンタ系ペンチャン待ち
ある時の配牌が下図。
とても上がれそうにない感のする配牌です。

あ~つまんないな~こんな配牌ばっかりで・・・
そんなこと思わないで、こんな時こそ麻雀の役作りを楽しもう!
第一打は![]() でも良いくらいです。
でも良いくらいです。
その後の捨て牌とテンパイの形はこうです。
11巡目にリーチ!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
待ちはペン![]()
第一打の![]() や
や![]() がかなり効果的で、
がかなり効果的で、![]() をロン上がりすることができました。
をロン上がりすることができました。
このように上手くいくことは、1日やっていれは1.2回はあるものです。
とんでもなく高い手になる時があるよ!
この精神で麻雀を楽しみましょう!

上手くいった時は幸せの絶頂でニコニコでご満悦だ!
といつもの私です。
3-2.引っかけで上がりやすいペンチャン待ち
テンパイがいつも両面待ちになるほど甘くないのが麻雀。
「俺は両面待ち以外はやらない!」
「ペンチャンやカンチャン待ちはしない!」
なんて言っていてはかなりイタイ方になってしまいます。
下図の捨て牌と、テンパイの形を見て下さい。
ドラは![]()
![]()
10巡目でリーチ!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
序盤からドラの![]() がトイツでなんとか上がりたい配牌。
がトイツでなんとか上がりたい配牌。
なんとか役無しテンパイしてのリーチ!
6巡目の![]() が効果的で、スジである
が効果的で、スジである![]() でロン上がりすることができました。
でロン上がりすることができました。
麻雀で引っかけと言われるケースです。
これを邪道!などと非難する方も中にはいますが、全くそんなことは心配ご無用!
言わせておけばよいです!
スジは安全とは限りません。
現物以外はすべてロンされる可能性を秘めています。
スジも含めて、振り込まないように何を捨てるか考えるのが麻雀。
それが麻雀の楽しいところです。
4.ペンチャンを確率的にデジタルで考える
4-1.ペンチャンと牌ランクBの孤立牌との比較
ここでは孤立した他の中張牌との比較を考えてみる。
牌ランクBとは2と8の数牌のこと。
詳しくは後述の章で確認して下さい。
実践でもよくあるケース!
![]()
![]() と
と![]() はどっちを大事にしたほ方がいいの?
はどっちを大事にしたほ方がいいの?
![]()
![]() と
と![]() ではどうなの?
ではどうなの?
こんな疑問にお答えします。
下図を見て下さい。
6巡目とします
上図の手牌に![]() を引く。
を引く。
すると・・・
「そっか![]() を残して
を残して![]() を引けば両面になるな!ペンチャンを落とそう!」
を引けば両面になるな!ペンチャンを落とそう!」
こんな風に考えていませんか?
![]() を引く確率と
を引く確率と![]() を引く確率は同じ、
を引く確率は同じ、![]() では即メンツとなります。
では即メンツとなります。
![]() を引けば同じくペンチャン。
を引けば同じくペンチャン。
そもそも![]() を残したとしても、
を残したとしても、![]() や
や![]() を引いてくるとも限りません。
を引いてくるとも限りません。
こんなケースでは![]() のツモ切りが正解。
のツモ切りが正解。
これは牌のランクに大きく関係します。
![]() と
と![]() では牌のランクが同じだからです。
では牌のランクが同じだからです。
これは後述していますから、知らない方は必ず見て下さい。
4-2.ペンチャンと牌ランクAの孤立牌との比較
同じ例で6巡目とします。
牌ランクAとは3~7の数牌のこと。
今度は![]() を引きました。
を引きました。
やはり![]()
![]()
![]() のメンツ以外はカンチャンとペンチャンばかり。
のメンツ以外はカンチャンとペンチャンばかり。
「そっか![]() を残して、
を残して、![]() か
か![]() を引けば両面になる!だからペンチャンを落とそう!」
を引けば両面になる!だからペンチャンを落とそう!」
こんな風に考えた方!
これはアリです。
![]() という数字は、
という数字は、![]() か
か![]() を引けば両面に、
を引けば両面に、![]() か
か![]() を引けばカンチャンになるというもの。
を引けばカンチャンになるというもの。
もしも両面になれば、ペンチャンと違い、上がる確率が4枚から8枚へと2倍になります。
このことから![]() を残し、ペンチャンを落とすことはアリなのです。
を残し、ペンチャンを落とすことはアリなのです。
これも牌のランクに関係します。
![]() は牌のランクAの牌なんです!
は牌のランクAの牌なんです!
3~7の牌が牌ランクAです。
これについても後述しましたから確認して下さい。
しかし注意が必要です。
6巡目としましたが、12巡目ではどうでしょうか?
麻雀の巡目は、下の表のように分かれています。
捨て牌は6枚切りで3段に分けて捨てて行きます。
捨て牌で考えるとわかりやすいでしょう。
| 序盤 | 1~6巡目 | 攻めの状態 メンツの素材集め |
| 中盤 | 7~12巡目 | 攻めか少しオリの状態 テンパイかイーシャンテン |
| 終盤 | 13巡目以上 | 攻めかオリの状態 上がりか流局 |
12巡というと終盤に向かうところです。
こんなケースで![]() をキープし、ペンチャンを落としてしまってはいけません。
をキープし、ペンチャンを落としてしまってはいけません。
あくまでも![]() は孤立牌。
は孤立牌。
その近くの牌を引いてこなくてはお話しになりません。
流局時にはテンパイ料が発生します。
大きい時は3000点の収入、出費になります。
ただテンパイかノーテンかだけでです!
ですから中盤最後から終盤においてはペンチャンが優先されます。
そして何よりも、この段階では振り込まないことが最優先です。
この解説はあくまでも手を進めることを前提にした話。
中盤から終盤ではテンパイしている方、リーチをかけている方がいるはずです!
くれぐれも振り込みにはご注意くださいませ!
下記サイトで牌のランクについてもっと詳しく解説しました。
5.ペンチャン待ちのリーチを守備の面で考えてみる
3-2章での手牌。
この手牌でドラはないとします。
しかも子のテンパイ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
いくら引っかけで出やすいとはいえ、リーチのみの子です。
この引っかけというのは、あなたひとりがリーチをかけている場合には有効です。
しかし、親やドラをかかえたやる気満々の他家から※追っかけリーチがかかればその効果は半分以下。
![]() で上がる確率はかなり下がってしまいます。
で上がる確率はかなり下がってしまいます。
リーチには、手を変えることができないというデメリットがあります。
このことをよく考えた上でのリーチが必要です。
このケースでのリーチは、
①ドラがある場合
②持ち点の少ない親で何としてでも親番をキープさせたい状況
こんなケースになると思います。
こんな風に考えておいて下さい。
6.必ず知っておきたいペンチャンの基礎知識

6-1.ペンチャン待ちとは
数牌の12か89で3か7を待つのがペンチャン待ちです。一般的には良い待ちとは言えません。
限定的で使いにくい待ちと言えるでしょう。
以下の6種類です。
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
6-2.他の待ちとの比較
待ちは広く構えるのが基本です。ペンチャン待ちの受け入れは狭く限定的で、待ちの中ではもっとも使いにくい待ちになっています。他の待ちと比較してみましょう。
◆多面待ち
色々な形がありますが、3種類以上の待ちを持つ形。
例えば上図の形なら![]()
![]()
![]() の3種類を待つ多面待ちです。
の3種類を待つ多面待ちです。
多面待ちはもっとも受け入れが広く理想的な形と言えます。
◆両面待ち
最もスタンダードな理想の待ちといえるのが両面待ち。
![]()
![]() と持ては
と持ては![]()
![]() 、
、![]()
![]() と持てば
と持てば![]()
![]() のように2種類の牌を待つ形です。
のように2種類の牌を待つ形です。
最大で8枚あることになります。
待ちはなるべくこの両面待ちになるようにするのが基本。
◆シャンポン待ち(シャボ待ち)
上図のように2種類の対子で待つ形。
数牌だけに限らず字牌も使うことができます。
2種類を待っていますが、そのうちの4牌をすでに自分で使っているので、残りの4牌を待つことになります。
◆カンチャン待ち
数牌の真ん中を待つ形です。
![]()
![]() という形で
という形で![]() を待ったり、
を待ったり、![]()
![]() という形で
という形で![]() を待つとカンチャン待ちになります。
を待つとカンチャン待ちになります。
ペンチャン待ちと同じく1種類4枚の牌を待つことになります。
ペンチャン待ちとの違いは両面への変化です。
この点に関しては次章で解説します。
◆単騎待ち
面子ではなく雀頭を作る待ちです。
上図のケースの場合には上がり牌は残り3枚。
すでに自分でもっている牌を使うので、あまり広い待ちではありません。
ですがどの牌でも使える自由度がメリットです。
6-3.牌のランクを知ろう
牌にはランクがあるのを知っていますか?
牌の切り方の基本にも通じる基礎ですから、必ず覚えて下さい。
Aランクから順にメンツになりやすいと考えて良い。
①牌ランクA
3~7の牌。
例えば![]() を使ったメンツは下の4種類。
を使ったメンツは下の4種類。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]()
これは![]() でも同じで4種類になる。
でも同じで4種類になる。
![]() より
より![]() の方がメンツになりやすいということはない。
の方がメンツになりやすいということはない。
ちなみに![]() を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
その有効牌は
![]() が残り3枚。
が残り3枚。
![]()
![]()
![]()
![]() が各4枚。
が各4枚。
全部で3+4×4=19枚
②牌ランクB
2と8の牌。
例えば![]() を使ったメンツは下の3種類。
を使ったメンツは下の3種類。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]()
同様に![]() を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
その有効牌は
![]() が残り3枚。
が残り3枚。
![]()
![]()
![]() が各4枚。
が各4枚。
全部で3+4×3=15枚
③牌ランクC
1と9の牌。
例えば![]() を使ったメンツは
を使ったメンツは
![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]() の2種類
の2種類
同様に![]() を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
その有効牌は
![]() が残り3枚。
が残り3枚。
![]()
![]() が各4枚。
が各4枚。
全部で3+4×2=11枚
④牌ランクD
字牌。
例えば![]() を使ったメンツは
を使ったメンツは
![]()
![]()
![]() の1種類
の1種類
同様に![]() を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
を自分がポツリと1枚だけ持っていると仮定すると、自分以外のところにメンツを作る上での有効牌を考えてみます。
その有効牌は
![]() が残り3枚。
が残り3枚。
全部で3枚
配牌から孤立牌を切り出す場合の基準になります。牌ランクCやDから捨てて行くのがセオリー。
イメージ的に3より5を大事にしそうだがそんなことはない。
6-4.ペンチャンから両面への変化を考える
ペンチャンが他の待ちに比べて不利なのは待ちの狭さだけではありません。
両面待ちへの変化が遠いという弱点もあります。
例えば![]()
![]() というペンチャン待ちが両面になるには、まず
というペンチャン待ちが両面になるには、まず![]() をツモって
をツモって![]()
![]() というカンチャン待ちにしなければいけません。
というカンチャン待ちにしなければいけません。
そして次に![]() をツモってくれば、やっと
をツモってくれば、やっと![]()
![]() の両面待ちに変化します。
の両面待ちに変化します。
つまり1度カンチャン待ちにならないと両面待ちに変化することができません。
それに比べてペンチャンは両面への変化に最低でも2手かかる。
これがペンチャンのデメリットの一つですので覚えておきましょう。
6-5ペンチャン待ちの符計算
点数計算はみなさんにとって悩みの種ですね!
ペンチャン待ちの符は何符つくか?
よく質問されます!
でも簡単です。
麻雀では、ペンチャン待ちに2点付きます。
下図を見て下さい。
この手牌では
![]()
![]()
![]() と
と![]()
![]()
![]() にそれぞれ8点。
にそれぞれ8点。
ペンチャン待ちに2点。
合計で18点。
もしこの手牌でリーチかけて上がると(ドラなし)
子で1600点、親で2400点です。
参考までに麻雀では
ペンチャン、カンチャン、タンキ待ちには2点付きます。
これを待ちに関する符と私は読んでいます。
悪い待ちには2点付くという感覚で覚えておいてください。
「点数計算が出来るようになりたい!」
と思ったらぜひ下記サイトで学んで下さい。
点数即答の私の計算方法を解説しました。
7.ペンチャンのまとめ
麻雀ではツモを予測することができません。
なのでどんなツモでも使えるように広く受け入れを取ることが基本です。
多面待ちや両面待ちなどが理想ですが、カンチャン待ちやペンチャン待ちのように狭い受け入れになってしまうことがあります。
特にペンチャン待ちは数字が限定されてしまう使いにくいもの。
タイミングをみてペンチャンを捨てていったり、或いはロン上がりが期待できるペンチャン待ちにしてみたり。
ペンチャン待ちで勝負する時は、追っかけリーチに弱い側面があることも覚えておいて下さい。
ペンチャンに関する記事を書くだけで、麻雀の奥深さを改めて感じています。
お相手は
NPO法人 健康麻雀グループ
理事長 河原 健治でした。
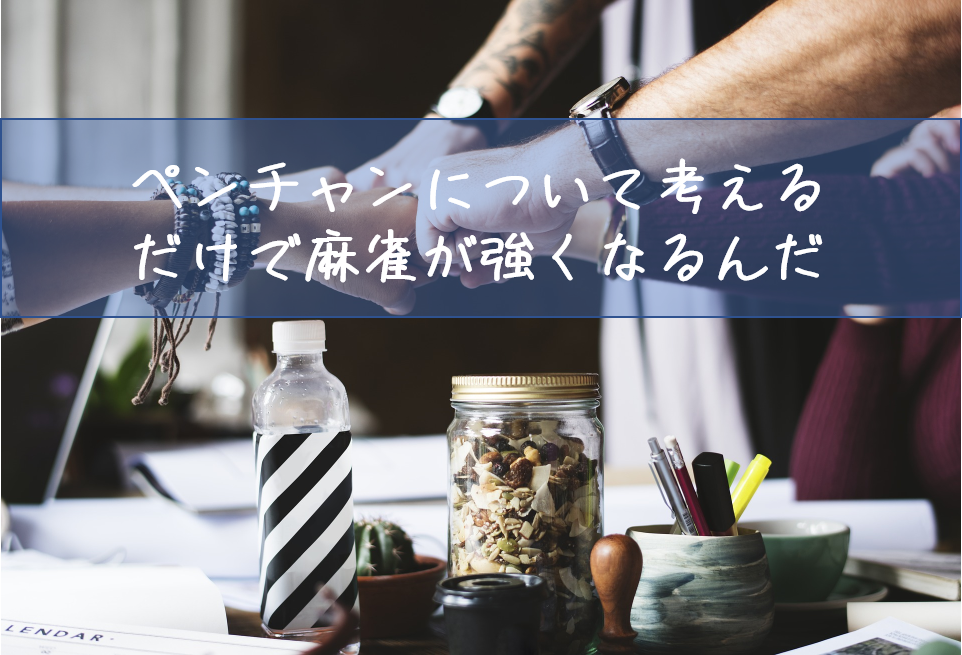










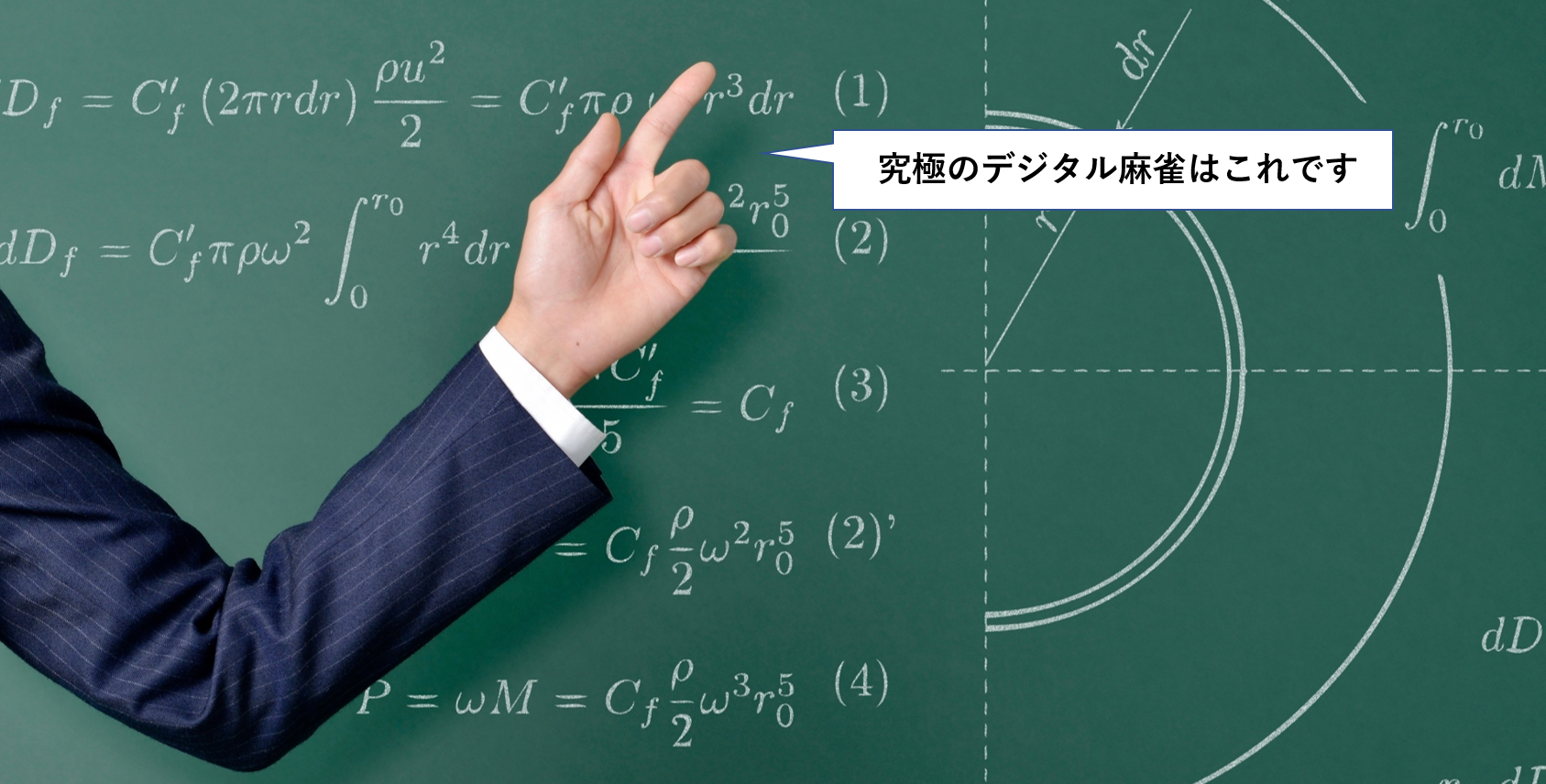

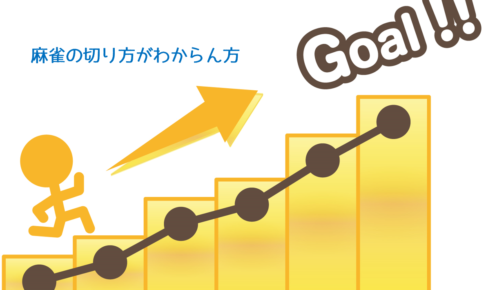



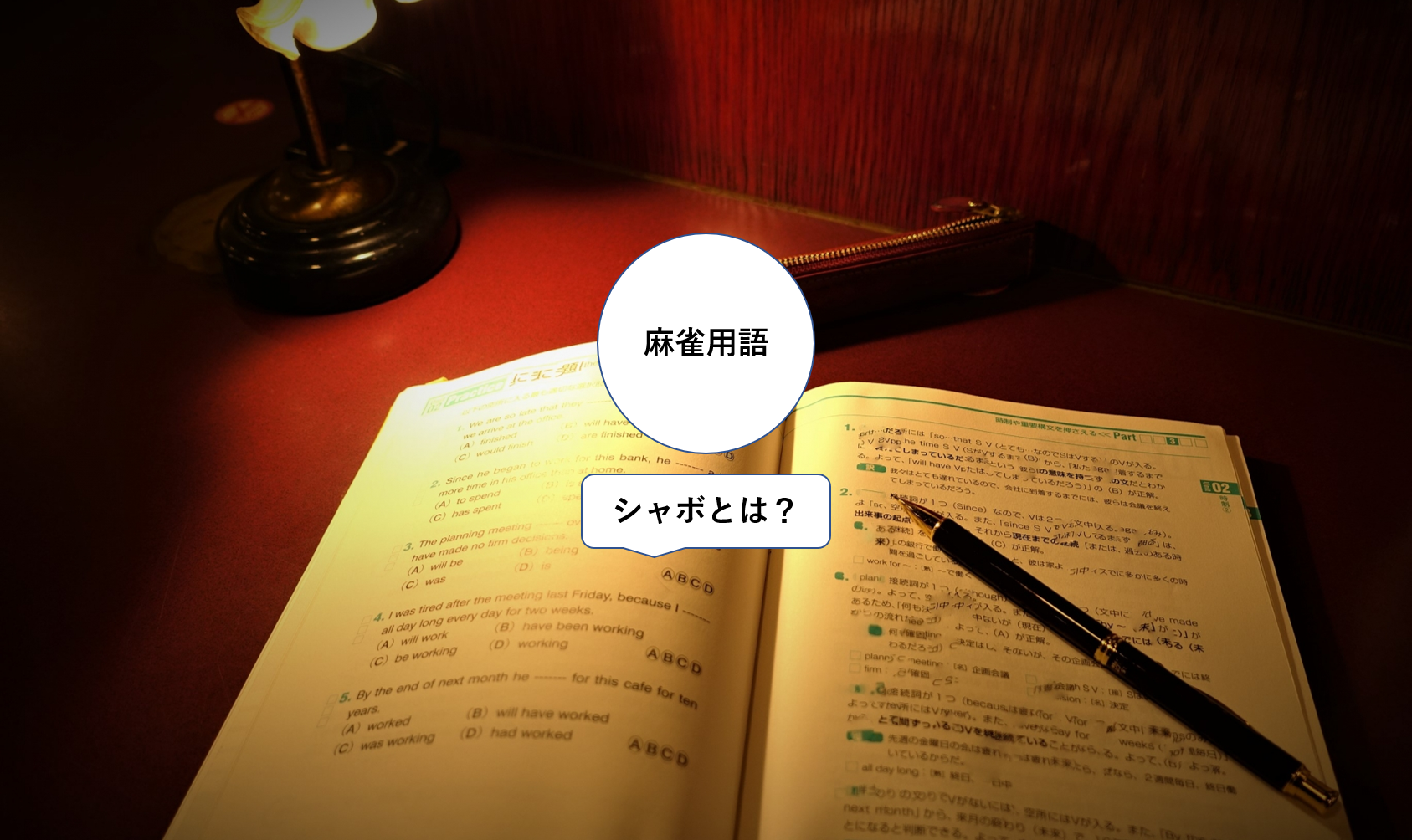


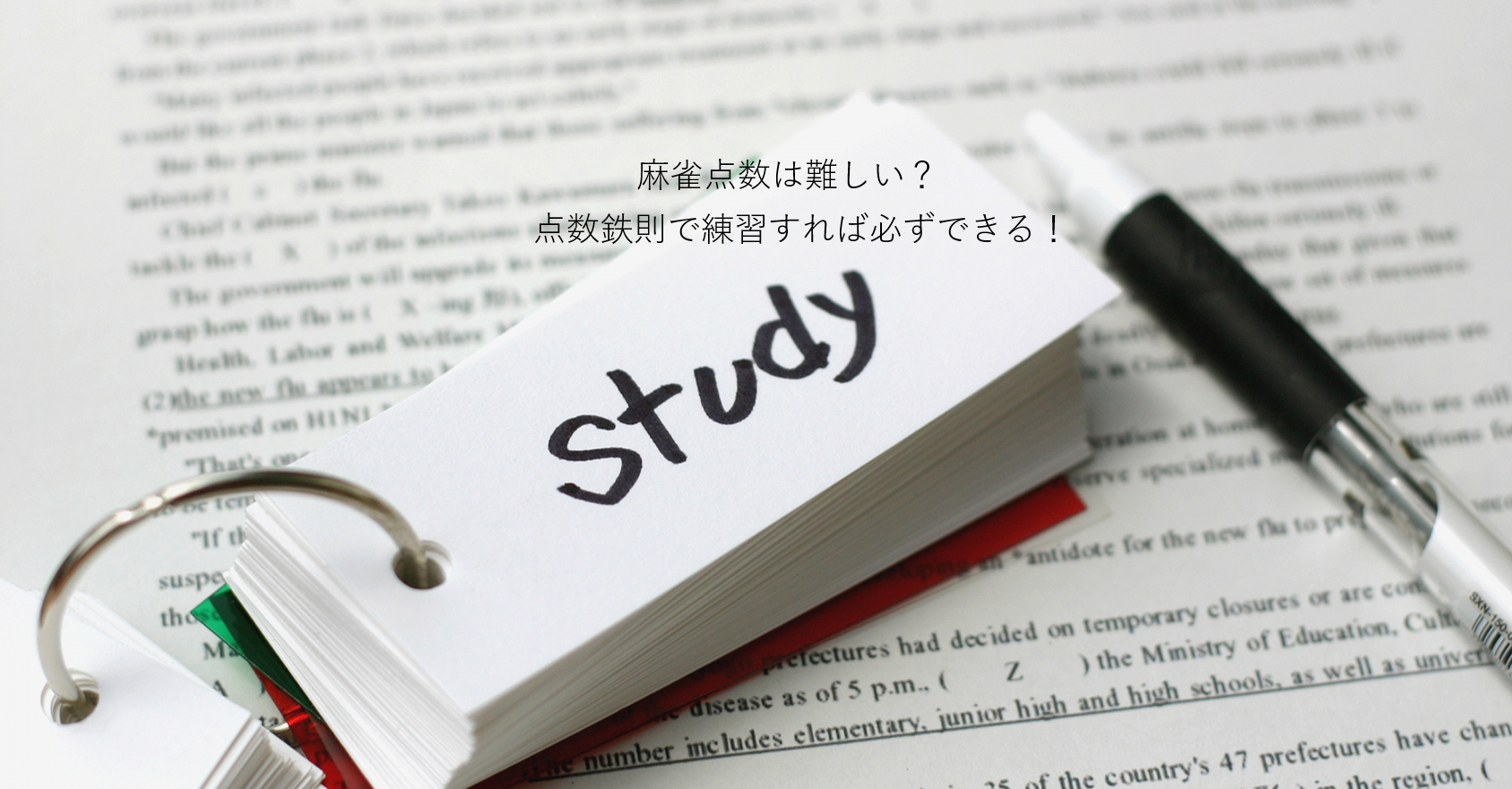




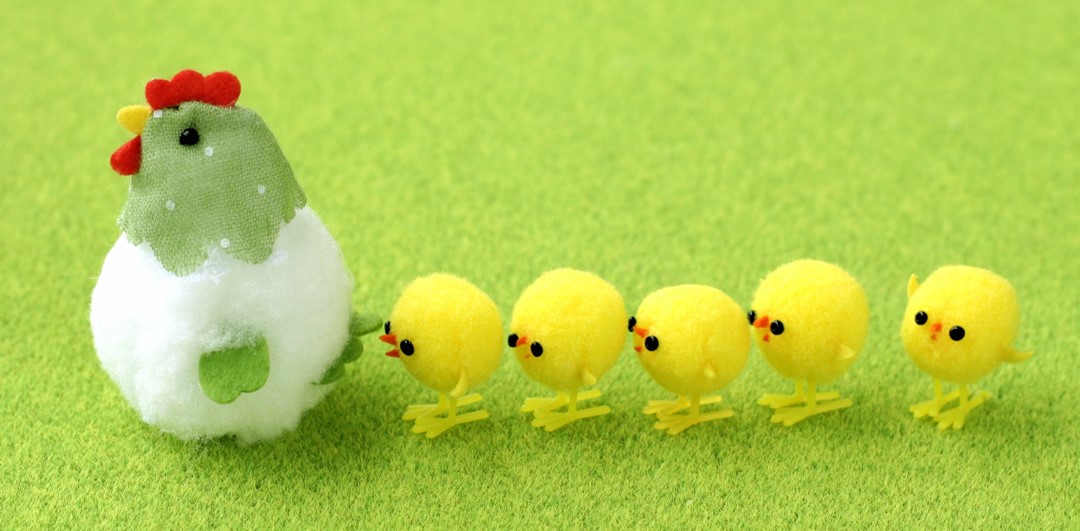




コメントを残す