リーチ後に「バシッ!バシッ!」と牌を毎回マットに叩きつける方がいます。
高齢者に多いような気もします・・・
30年以上麻雀をしている男性なら一度は経験あるかもしれませんね。
そうです!昔はこんな行為が横行していたのは事実です。
麻雀教室でキチンとマナーを学ぶなどあり得ないことでしたもんね!

私も引きヅモとは違いますが、リーチ後や高い手牌を上がった時に牌をビシッと叩きつけていました。
ビシッといい音がなると気持ちのいいものでした・・・
こんにちは千葉県柏市 NPO法人 健康麻雀グループの河原 健治です。
でも現在では、これは対戦相手に大変嫌われる行為になっています。
今回は麻雀のマナー違反の一つである引きヅモについて解説します。
あなたが知らないうちに迷惑行為をしてしまうことがないように!
いきなり注意されたり、わけもなく誘ってもらえなくなったりしないように!
それは困りますからね!引きヅモについて知っておきましょう。
↓当店の公式サイトもご覧ください↓
はじめてのご参加の方全員に¥3000分の割引券をプレゼント!
1.引きヅモとは?動画で見てみよう!
引きヅモとは、リーチ後に牌をツモる際に、上がったわけでもないのに毎回牌を表にして手元の縁までぶつけるように引くツモり方です。
まずは引きヅモがわからない方のために動画を見て下さい。
これをやられると周りは「ツモ上がりかな?」と勘違いしてしまいます。
雀荘などでは引きヅモを「誤ツモ」として罰符を取るところもあるぐらいです。
特にリーチをかけたときなどは引きヅモは迷惑な行為です。
引きヅモのようなオーバーアクションは注目を集めますが、純粋な勝負の駆け引きには邪魔です。
価値の高い大きい手などをテンパイ(あと1牌で上がれること)したときなど、ツモに気持ちが入ってしまいますが自制しましょう。
ドキドキしていても正しいフォームでツモることが大切です。
2.なぜ引きヅモがマナー違反なのか
2-1.麻雀はテンポよく行うゲーム
勝負の局面になればツモに気持ちが入ることもあるでしょう。
ですが麻雀は4人で行うもので、周りの迷惑を考えなくてはいけません。
そもそも!
麻雀はテンポよく行うゲームです。
誰かが無駄な時間を使うとイライラするものです。
ツモ上がりしたわけでもないのに、1回1回牌を手前に置くわけですから時間の無駄になります。
ツモを必要以上に目立たせる引きヅモは、他人から見て紛らわしいものです。
ツモった牌を表にしたまま手元に置くのは、ツモで上がった場合だけです。
いくら手を離さず「ツモ」と宣言していないからといって、そのような行為は場に混乱を招きます。
例えば引きヅモをした瞬間に、他の人が自分の手を伏せ目の前の山を崩してしまったとします。
これは「ツモ上がりされた」と勘違いしたほうが悪いのでしょうか?
「引きヅモ禁止」のルールがない場では難しい所です。
引きヅモをしたほうにも責任があるといえるでしょう。
このような混乱を起こさないためにも引きヅモのような行為をしてはいけません。
2-2.道具は大切に扱いましょう

引きヅモがマナー違反になっている理由の一つに、道具を荒く扱っていることがあります。
オーバーアクションで牌を叩き付けたり、縁に勢いよくひきつけるのは道具を傷める可能性があります。
牌や雀卓や縁に傷ができてしまったらお店は損害を被ってしまいます。
そして道具の損傷よりも痛いのが見た目の美しさです。
麻雀は知的なゲームで、麻雀を通じた他人との交流に醍醐味があります。
そこに過激なアクションや過度な動きは必要ありません。
まったく不必要なそれらの動きは道具を傷めるだけでなく、見た目も美しくないので控えるべきです。
3.引きヅモをしない正しいフォームとは(動画で確認)
ツモは正しいフォームで行いましょう。
背を伸ばし、まっすぐ手を牌に伸ばします。ツモって来た牌は手元で確認し、一度手牌に置くかそのまま打牌(牌を捨てること)するのが正しいツモのやりかたです。
長い間についてしまったクセなのかもしれません。
ですが他人に不快な想いをさせていいわけがありませんよね。
ここで土田浩翔先生の正しいツモを見てみましょう!
特にリーチをかけたときなどはツモに注目が集まりますので、表にして叩き付けてそのまま河(捨て牌の場所)に捨てるという行為はいけません。
他人の注目をわざと集めるのは作戦としても下の下です。
価値の高い手を作っているときほど冷静に、そして淡々とツモを行うべきです。
余計な注目を集めることは警戒を呼ぶことになります。
心臓がバクバクしてもいつもと変わらないツモを心がけましょう。

麻雀は4人集まらなければできないゲーム。あの方は引きヅモするからやりたくない!
なんて思われてたら悲しいですよね!
4.引きヅモされた場合のベストな対処方法

同卓した方が引きヅモした場合に、どう対処したらよいでしょうか?
「なんか怖そうな方だし・・・」
「とてもじゃないけど注意する勇気はありませーん」
こんな時はありますよね!
一番ベストな対応方法はコレです。
①まずは自分で注意しないこと!
②お手洗いにいくフリをして、店員さんに報告し注意してもらう。
③それでも直らない場合は、店員さんに席を変えてもらいます。
(店員さんは慣れていますから上手にやってくれるはずです)
マナーだからといって直接注意は禁物です。
どんな性格の方かはわかりません。
いきなりカッとなる方もおられます。
もしそのようなことになったら、あなたではもう対処できないはずです。
そこまでならないにしても、気まずい雰囲気のまま1時間も同卓するのは全員がキツーイはず。
他のマナー、ルールの場合もそうですが、店員さんに任せることが大事なので覚えておいて下さい。
5.まとめ
引きヅモは余計な注目を集めるだけでなく、道具も傷めてしまう行為です。
ツモは淡々と行うことが警戒をされにくいので上がりやすく、そして美しいやり方です。
ダイナミックに叩き付けて注目を浴びるのは、自分の目立ちたい欲が表にでてしまっている恥ずかしいことなのです。
長年のクセとはいえ直すことは難しいかもしれませんが、4人が楽しく麻雀ができなくてはいけません。
「あの方となら一緒に麻雀がしたい」
こんな風に思ってもらえるようなマナーを身に付けたいものですね!
お相手はNPO法人 健康麻雀グループ
河原 健治でした。


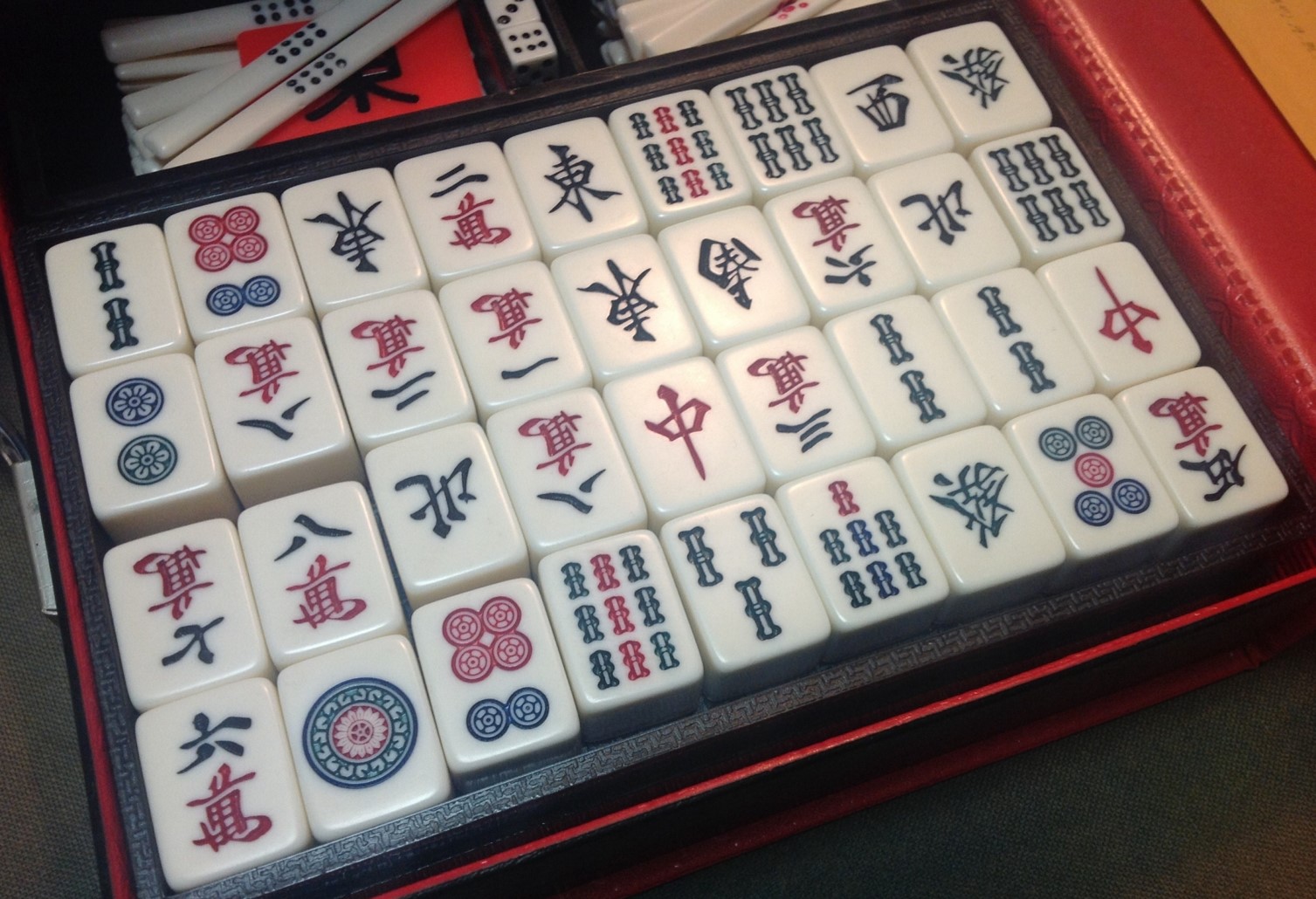





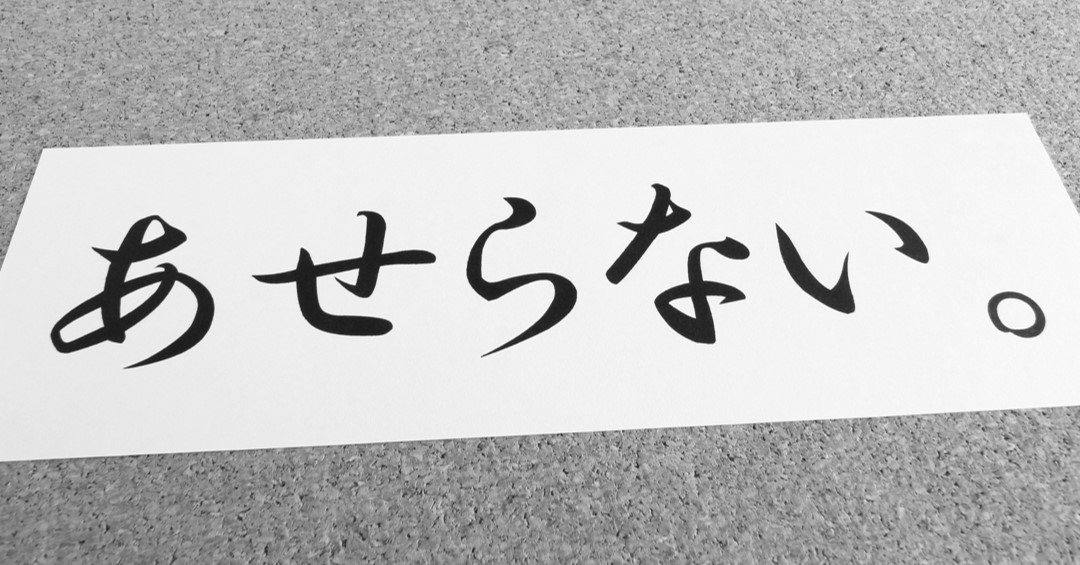


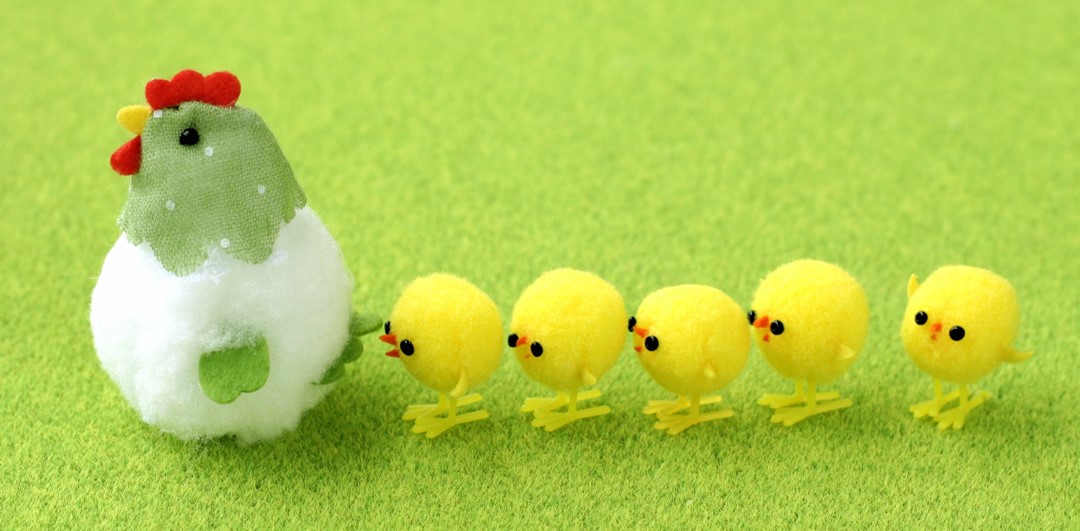
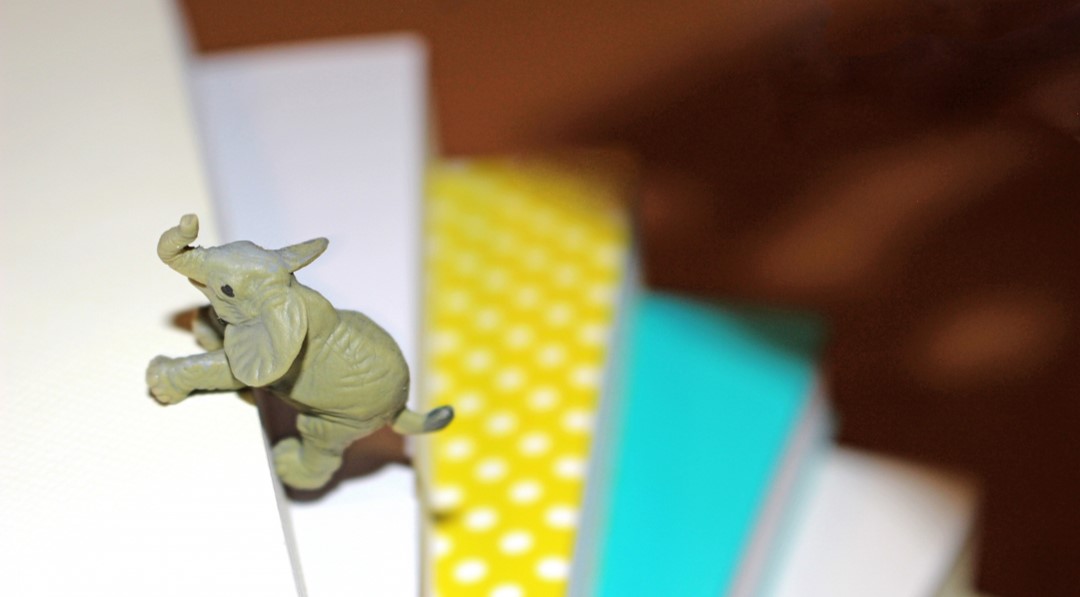
コメントを残す