シャンテン(向聴)とは?
シャンテンとは、麻雀の聴牌までに必要な手数のこと
麻雀の対局中や誰かが上がった時などに、※聴牌(テンパイ)という言葉や※一向聴(イーシャンテン)という言葉をよく聞くと思います。
聴牌の意味は何となく理解している人も、シャンテンという言葉は意味がよくわからないという人もいるのではないでしょうか?
自分のシャンテン数を把握する。つまり自分の手牌の進行具合がわかっていることは大切です。テンパイまで程遠いのにリーチ者に振り込むようなことがあってもいけません。
今回はそのシャンテン(向聴)について詳しく解説していきます。
■聴牌(テンパイ)についてもっと詳しくは
ケース別解説なら簡単!麻雀テンパイ(聴牌)に一歩近づくための打ち方とはvol.14
■一向聴(イーシャンテン)についてもっと詳しく
みんなが知りたい麻雀のイーシャンテンの意味と注意すべきポイントとは
1.麻雀のシャンテン(向聴)とは?
シャンテン(向聴)という言葉は、麻雀用語としては頻繁に登場する用語になりますが、あまり単独では使用しません。
シャンテン(向聴)の意味やシャンテン数についての説明を簡単にしていきます。
1-1.シャンテンの意味
麻雀で聴牌というのは、上がりまで残り1牌必要な状態ですが、シャンテンは、聴牌までに必要な手数の事をいいます。
つまり、一向牌(イーシャンテン)は上がりまでは最低2牌必要ですが、聴牌までは1牌必要な状態という事になります。
図A-1)聴牌の状態 ![]() と
と![]() の待ち
の待ち
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
図A-2イーシャンテンの状態
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() の7種類が来れば聴牌になるイーシャンテン
の7種類が来れば聴牌になるイーシャンテン
図A-1は、![]() と
と![]() 待ちの聴牌の形ですので、さほど難しくはありませんが、図A-2の状態はその一歩手前のイーシャンテンの状態になります。
待ちの聴牌の形ですので、さほど難しくはありませんが、図A-2の状態はその一歩手前のイーシャンテンの状態になります。
何が来れば聴牌か?と考えた時に、少し難しくなります。それでは見てみましょう。
■![]() をツモ、
をツモ、![]() を打牌、
を打牌、![]() 待ちの聴牌
待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■![]() をツモ、
をツモ、![]() を打牌、
を打牌、![]()
![]() 待ちの聴牌
待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■![]() をツモ、
をツモ、![]() を打牌、
を打牌、![]()
![]() 待ちの聴牌
待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■![]() をツモ、
をツモ、![]() を打牌、
を打牌、![]()
![]() 待ちの聴牌
待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■![]() をツモ、
をツモ、![]() を打牌、
を打牌、![]() 待ちの聴牌
待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■![]() をツモ、
をツモ、![]() か
か![]() を打牌、
を打牌、![]() か
か![]() ※単騎待ちの聴牌
※単騎待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■![]() をツモ、
をツモ、![]() を打牌、
を打牌、![]()
![]() シャボ待ちの聴牌
シャボ待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
当たり前の事ですが、聴牌よりもイーシャンテンの方が、待つ牌は多くなりますし、二向牌になれば更に多くなることが基本です。
1-2.麻雀で重要なシャンテン数
シャンテン数というのは、文字通り数字が増えれば聴牌までが遠くなり、小さな数字になればなるほど聴牌に近づいていきます。
聴牌をはじめ、一向聴(イーシャンテン)や二向聴(リャンシャンテン)までは、実際の対局の中でもでてくる麻雀用語です。
実際には、その先の三向聴以降もありますので、一応掲載をしておきますので、余裕があれば、覚えておくと良いと思います。
聴牌
一向聴 イーシャンテン 聴牌まで、あと1枚の状態
二向聴 リャンシャンテン 聴牌まで、あと2枚の状態
三向聴 サンシャンテン 聴牌まで、あと3枚の状態
四向聴 スーシャンテン 聴牌まで、あと4枚の状態
五向聴 ウーシャンテン 聴牌まで、あと5枚の状態
六向聴 ローシャンテン 聴牌まで、あと6枚の状態
麻雀で最も聴牌までにかかるシャンテン数は、限りなくあるようですが、基本的に六シャンテンが最大になります。
どのような配牌になっていても、七対子が上がりと考えれば、六シャンテンになっている事がわかります。
2.麻雀のシャンテンの考え方
麻雀で強くなるには、シャンテンを理解することはとても重要になりますが、強い人は対局中にも常に自身が何向聴か意識しながら打つ人もいます。
また、何シャンテンかは理解していなくても、聴牌までの道筋は自分なりに作っている人が多いといえます。
2-1.シャンテンの基本は聴牌までの道
シャンテンの数字は、基本的には1つ減るのが基本ですが、打ち方によっては、1度遠回りをする事もあります。
例)下図の一シャンテンの手牌で![]() ツモだとします
ツモだとします
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() を捨てればテンパイします。つまりシャンテン数はゼロ。
を捨てればテンパイします。つまりシャンテン数はゼロ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
しかしながら![]() のカンチャン待ち、※タンヤオも付きません。ここはそのまま
のカンチャン待ち、※タンヤオも付きません。ここはそのまま![]() を※ツモ切りして元のイーシャンテンの手牌に戻します。向聴数は1となります。
を※ツモ切りして元のイーシャンテンの手牌に戻します。向聴数は1となります。
このようなことは中級者以上になればよくやることですから覚えておいた方が良いでしょう。
シャンテン数は多くなることはありますが、上がりを目指すと言う事は、基本的に1つずつ数字が減っていく仕組みになっています。
2-2.受け入れ牌を考えよう
受け入れ牌というのは、聴牌やイーシャンテンになるのに待っている牌の事で、最終的に受け入れ牌が多いという事は、多面待ちでの聴牌という事になります。
図B-1)![]()
![]() 待ちの聴牌
待ちの聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
図B-1の受け入れ牌は、![]()
![]() となり、一般的には、
となり、一般的には、![]() と
と![]() の両面待ち(リャンメン待ち)という言い方をします。
の両面待ち(リャンメン待ち)という言い方をします。
図B-2)![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() の7種類が来れば聴牌
の7種類が来れば聴牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
図B-2の聴牌への受け入れ牌は、![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() となり、理想はともかく7種類の牌がこの状態での受け入れ牌という事になります。
となり、理想はともかく7種類の牌がこの状態での受け入れ牌という事になります。
3.麻雀の聴牌とシャンテン数の実践的な考え方
麻雀を始めたばかりの時であれば、とにかく早い段階で聴牌をして、※リーチをかけるというのが、目標にもなります。
麻雀で少しでも上がる確率を上げるには、アナログ的な要素もありますが、基本的により多くの受け入れ牌をつくる事が重要になります。
3-1.受け入れ牌を常に多く考える
受け入れ牌を多くしたい時に最も考えなくてはいけないのが、上がる状態までのイメージになります。
初心者にありがちなパターンは、早い段階での決め打ちがあり、3巡目程度で役を決めつけた打ち方をする人もいます。
確かにケースによっては、決め打ちも可能ですが、早い段階での決め打ちは、他家にもバレやすいので、なかなか振込みをしてくれません。
また、他家に逆手に取られて、危険牌とわかっていながら捨牌をする状況になる事も考えらえます。
常に受け入れ牌を多く待てるような打ち筋を身につけることで、より聴牌までの道のりが近くなると考えられます。
例)下図は二シャンテンの手牌です
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この手牌に![]() のツモです。一見すると
のツモです。一見すると![]() を捨ててイーシャンテンにしそうです。でもよく考えてみて下さい。ソウズの部分は
を捨ててイーシャンテンにしそうです。でもよく考えてみて下さい。ソウズの部分は![]()
![]() となっていて両面ではなく、形がよくありません。ここは
となっていて両面ではなく、形がよくありません。ここは![]() を残し、打
を残し、打![]() としましょう。マンズの
としましょう。マンズの![]()
![]()
![]() の部分は
の部分は![]()
![]()
![]() となり、
となり、![]() がいらなくなるケースが多いです。
がいらなくなるケースが多いです。
つまりピンズの下の部分である![]() をわざわざ残し、そこで
をわざわざ残し、そこで![]() か
か![]() を引いても良いようにキープします。確かに
を引いても良いようにキープします。確かに![]() を捨てるということは
を捨てるということは![]() や
や![]() が来てしまった時にはリスクとなります。しかしここはなるべく受け入れを広く考え打
が来てしまった時にはリスクとなります。しかしここはなるべく受け入れを広く考え打![]() とする打ち方もアリなのです。
とする打ち方もアリなのです。
このことは次章にもつながっていきます。
3-2.聴牌時に良い待ちを考える
いくら早くシャンテン数を減らしても、聴牌時の待ちが悪ければ結果的に上がれなくなる危険性が多くなります。
最終的な聴牌時の待ちを広くすることが最も重要な事になりますが、一般的には二向聴(リャンシャンテン)以降が最も勝負どころだといえます。
もちろん、二シャンテンにするまでの工程も常に受け入れ牌の数を多くすることを意識することが大切になりますが、そこまで都合よくツモはできません。
二シャンテンくらいになると、他家の手もかなり進んでいますし、中には聴牌になっている人もいる可能性もあります。
このような時は、自分の聴牌時の形や役を考慮に入れた中で、勝負をするのか、他家の河を見ながら比較的安全に降りるのかを決めるポイントにもなります。
常に受け入れ牌の数が多くなっている事が有利に展開できる事につながりますので、意識をしながら麻雀をすると良いといえます。
4.シャンテンの間違いと押し引きのポイント
向聴(シャンテン)の意味を間違えるとすれば、あくまでも聴牌までの数であって上がりまでの数ではないという事になります。
技術的なポイントは、やはり受け入れ牌をいかに多くできるかが、ポイントになるといえます。
自分が今、何シャンテンになっているかが理解できるようになると麻雀の技術は確実に上がっていると考えられます。そして相手のテンパイへの対処も落ち着いたものに変わってくるでしょう。
つまり相手がリーチなどテンパイしている時の対応は下記のようなイメージです。
■自分は二シャンテンの場合→オリ
■自分は一シャンテンの場合→3割勝負、7割オリ
■自分もテンパイの場合→9割勝負、1割オリ
5.まとめ
麻雀の対局中には、あまり意識して何シャンテンという考え方をしない人も多いと思いますが、常に受け入れ牌を多く持つことは重要になります。
仮に良い形での二シャンテンやイーシャンテンの形であれば、他家がリーチをしても、安全牌を捨牌しながら、現状を維持することも可能になります。
自分の手牌の進行度(シャンテン数)を把握し、3人の相手にどう対処するのかを考えます。これが麻雀の押し引きにもつながって行きます。
冷静に判断できるようになれば、あなたのスキルもまたひとつアップできることになるでしょう。
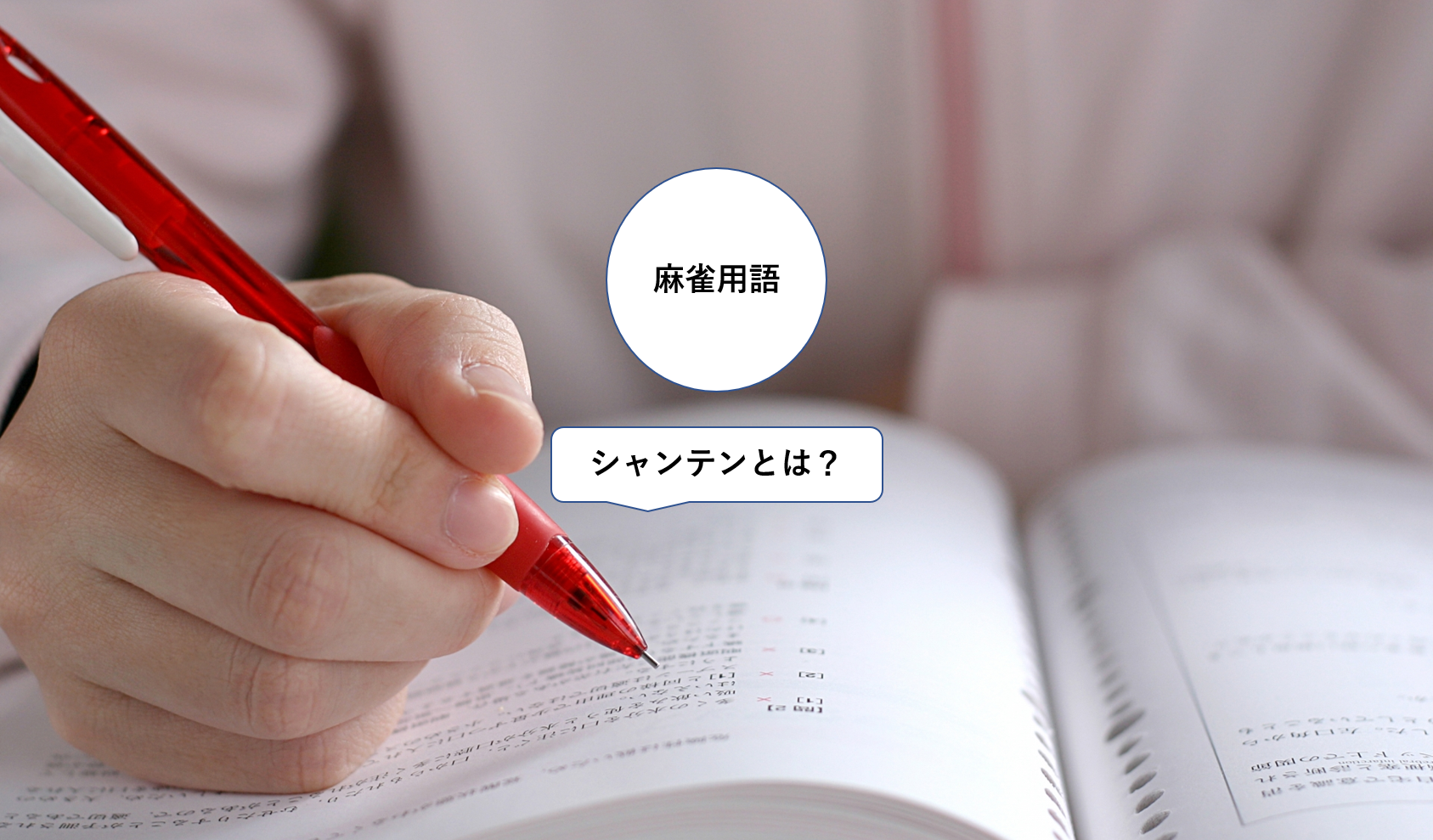










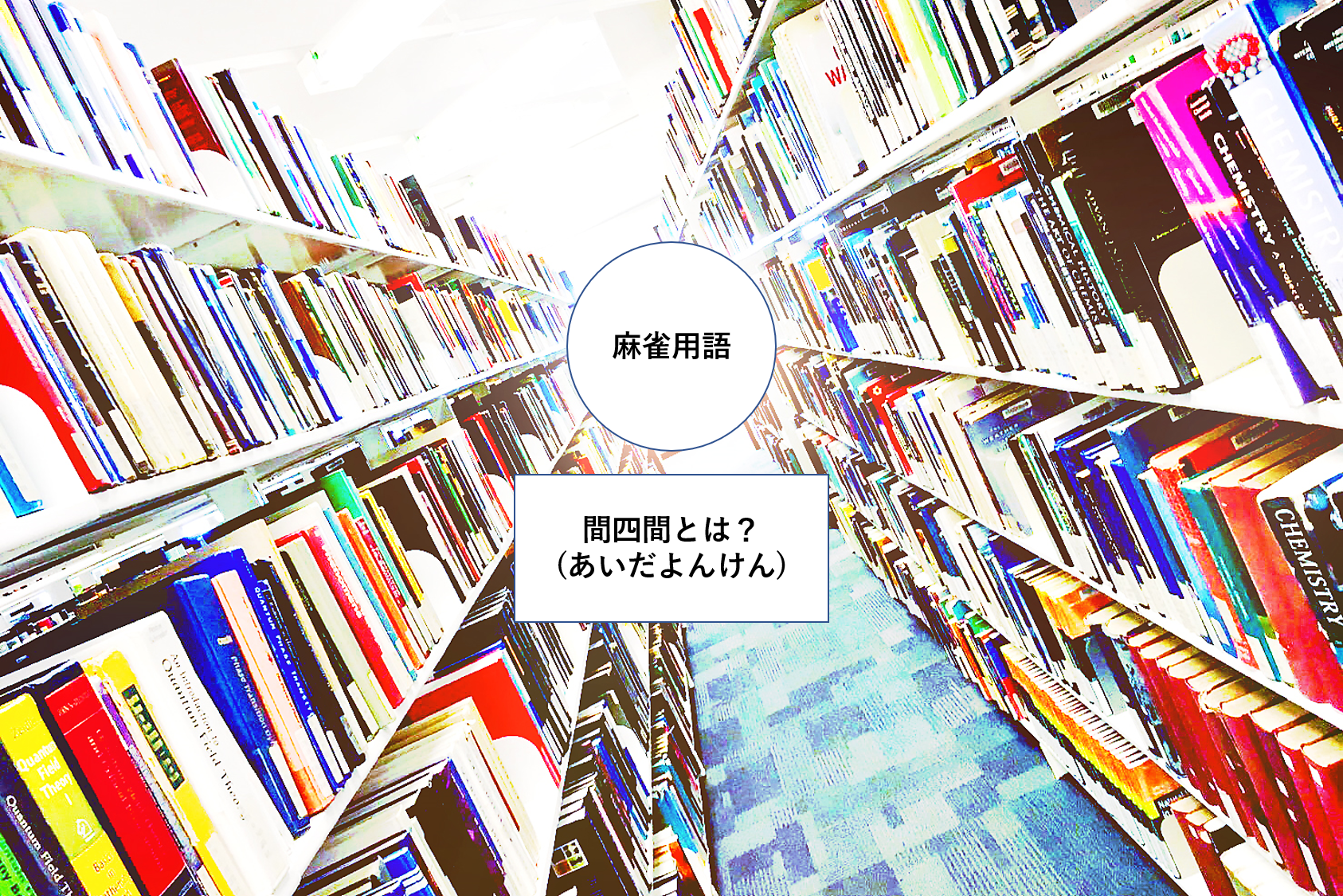





コメントを残す